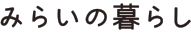スマートロック SESAMEの個人的に気に入っているところは、鍵の開閉機能を電子的なものに「置き換える」のではなく、単に機能を「追加する」だけなところ。つまり、今まで通り物理的な鍵による開閉もできるところです。
これによって「もし鍵(SESAME)が壊れても心配いらない」という安心感がついてきます。普段冒険をしない保守的な人間にこそ、SESAMEを使って欲しいと思う理由について、過去の体験と一緒に紹介します。
鍵が壊れた
研究室の定例報告会開始時刻が迫り、先輩方はすでに会議室に向かわれていました。私も早く出発せねば、と資料を手に抱えて居室を後にします。
私の所属していた研究室では、最後に居室を出る人間が施錠することが決まりです。そのときもいつもの動作で、ただし急いでいたため少々乱暴に鍵を閉めました。
鍵を差し込み、回して、抜く。この「回して抜く」という一連の動作をスムーズにし過ぎた結果、鍵の先端は鍵穴内部に残ったまま、持ち手の部分から捻じ切れてしまいました。
一応施錠は出来ていたので、鍵穴内部に残っていた鍵の先端をなんとか引っ張り出し、その場は急いで会議室へ向かいます。後から同期に鍵を借り、大学近くの鍵屋で合鍵を作ることなってしまいました。
仕方がないので、「この前急いでたら鍵壊れた」というネタとして消化したのですが、それなりに受けたように記憶しています。筆者が大学時代の話です。

家鍵だったらやばかったなと
思えば研究室の居室の鍵はかなりチープなものでした。家鍵よりも薄く、折れやすそうな構造だったと記憶しています。とはいえネットを見てみれば、家鍵が同じような壊れ方をして大変だった方々のエピソードが面白おかしく掲載されています。
もし家鍵が壊れてしまった場合、一人暮らしであれば鍵屋さんが到着するまでは家に入れないわけで、時間帯次第で、その日はどこか別の場所に滞在することになるでしょう。
壊れたのが家鍵でなかったことは不幸中の幸いです。
SESAMEで安心を追加する
時は流れ、CANDY HOUSEさんの SESAMEを使うようになって、もし一人暮らしで家鍵が唐突に壊れたとしてもこれで安心だな、ということに気付きました。少なくとも自宅に入れないということはないはずです。
SESAME Touchを導入しているため、普段の鍵の開閉は手指があれば問題ありません。家鍵を何らかの理由で紛失しても家には入れます。
逆に、電池切れなどで SESAMEが機能しないこともあるかもしれませんが、その場合は常に鞄に忍ばせてある物理鍵を使って開錠すればよいだけです。
冒頭でも述べましたが、SESAMEを導入したからと言って物理鍵が使えなくなるわけではありません。単に選択肢が増えるだけです。また、緊急時の対策も増えます。
SESAMEは、ついつい「もしこうなったらどうしよう」という心配に囚われてしまう方にこそおすすめです。そういう意味で SESAMEは安心を追加するガジェットだと言えるかもしれません。
キャンディハウス SESAME5 セサミ5 スマートロック オートロック 鍵 スマホで操作 Alexa Google Home Apple AppleWatch 遠隔対応 工事不要 後付け
これは本当に便利!毎日の鍵のストレスから解放
キャンディハウス SESAME TOUCH セサミタッチ 指紋認証パッド ICカードリーダー Suica対応 PASMO対応 Apple watch 工事不要 取付カンタン 防犯対策
使ってみたら、もう鍵には戻れない!
強いられない
また、新しい技術やガジェットの導入で今までのやり方を変えるのが嫌だ、という人は多いと思います。私もその一人です。スマートでシンプルな生活スタイルには憧れますが、それを強制されるのは癪でしょう。
しかし、SESAMEは「使ってやってもいいかも」と思えるときまで静かに待っていてくれます。家族の中で「普通の鍵で開けたい」というメンバーがいたとして、その人を説き伏せる必要はないのです。普通の鍵を使う人と、SESAMEを使う人が共存できます。
共同鍵における経済合理性
研究室の話に戻りますが、私が所属していた研究室は各学年に 5, 6人、ドクターも含めて計 20人ほどの学生が所属していました。その学生全員が鍵を持っていたので、1本 500円だとしても 1万円ほどが合鍵作成に使われていたはずです。
SESAME5と SESAME Touchを合わせて購入しても 9千円程度。20人程度なら問題なく登録できます。このように特殊なケースに限って言えば、SESAMEの導入がコスト面から見ても十分に合理的な選択肢になり得る、と言えるでしょう。
SESAMEの開錠は逐一記録されますし、盗難被害の防止にも役立ちます。こうした限定的なケースに限って言えば、総合的な観点から使わない理由はあまりなく、問題は知名度だけです。
誰もが安心して、より低コストで便利な生活ができるよう、今後も情報を発信していきたいと思います。