毎日休みなく家事や育児に追われる主婦にとって、日常生活でもう少しゆとりをもちたいと考える方も少なくないのではないでしょうか。そのためにも、日々の家事をできるだけ簡単に効率よくこなしたいですよね。そんな家事楽を叶える方法のひとつに「スマートホーム」があります。本記事では「スマートホームを実現させるために必要なネットワーク」の選び方から導入方法の基本について解説しています。手軽に取り入れられる方法もご紹介しているので、ぜひご覧ください!
スマートホームで家事楽できるのはなぜ?

スマートホームにすると、スマホひとつで外出先から鍵の開閉やエアコンなど複数の家電操作が可能になります。それらは、家電をネットワークで繋ぐ「IoT(アイ オー ティー)」技術によって叶えられます。IoTとは、モノのインターネットを意味するInternet of Thingsの略です。IoTによってできることを大きく分けると次の3つです。
- 遠隔によるモノの操作
- 遠隔による状態の把握
- モノ同士による通信
例えば、外出先からエアコンや洗濯機など家電のオンオフや鍵の開閉などの操作ができるようになります。また、冷蔵庫にある食材や個数の確認も可能になるため、買い忘れや余分な購入を防げます。食材によるレシピ提案を可能にすることもできるため、毎日の献立に頭を悩ませている主婦にとってはありがたい機能ですよね。
他にも「牛乳がなくなりそう」など冷蔵庫からスマホに通知がきたり、洗濯機の終了を通知してくれたりすることもネットワークの設置で可能になります。
ただし、家電やドアロックを一つのネットワークに接続してスムーズに操作するためには、共通の「言葉」や「ルール」が必要です。このような共通のルールを「規格」と呼びます。
ネットワークを繋げるための主な通信方法5つとは

スマートホームでは家電同士が「ネットワーク」で繋がっているため、複数の家電をひとつのスマートフォンやスマートスピーカー・リモコンなどで一括操作ができます。また、通信方法には、Wi-FiやBluetoothなど5つの主要タイプがあります。通信方法には、用途別に最適なタイプがあるため、以下のように比較しました。
| Wi-Fi | Zigbee | Bluetooth | Thread | Z-Wave | |
| 特徴 | ルーターでデバイス接続 | 省エネ設計 | スマホ直結 | 次世代のスマートホーム向け(Appleが積極的に利用) | 幅広い相互運用性 |
| 電力 | △(高) | ◎(低) | ○(低) | ◎(低) | ◎(低) |
| メリット | ・高速広範囲の通信 ・多くのデバイスに対応 | ・消費電力が低い ・メッシュネットワーク※1で通信範囲拡大 ・月額費用不要 | ・消費電力が非常に低い
・ハブ※2不要 ・月額費用不要 | ・メッシュネットワーク※2対応 ・高いセキュリティ ・超低消費電力 | ・製品の互換性が高い ・メッシュネットワーク※1対応 ・Wi-Fiの干渉を受けにくい |
| デメリット | ・電波干渉に弱い
・消費電力は高め・セキュリティリスクあり | ・通信速度がそれほど早くない
・ハブ※2が必要 | ・通信範囲が短い
・同時接続できる数が少なめ | ・対応するデバイスが少なめ
・ハブ※2が必要 | ・対応するデバイスが少なめ
・通信速度が遅め |
| 工事費用(システムや規模によって変わる) | 0円(光回線は費用あり) | ハブ※2設置(数千円から1万円ほど) | 0円 | ルーター設置(数千円から数万円ほど) | ハブ※2設置(数千円から2万円ほど) |
※1 メッシュネットワークとはメッシュ(網目)のようにネットワークが繋がりあう
※2 ハブとは多数の機械やデバイスを繋げるための中心となるもの
主婦目線で選ぶ!最適なホームネットワークとは

住まいや家族、使用したい家電と生活スタイルに合わせた最適なホームネットワークの選び方を解説します。
Wi-Fiを選ぶときに押さえておきたい3つの基本
- 同時接続数:家族4人+家電20台なら「30台対応」ルーター必須
- メッシュ機能:2階建て以上の戸建てなら中継機内蔵型かメッシュWi-Fi※1がおすすめ
- セキュリティ:WPA3対応ならハッキングリスク半減
同時接続数が多くなる場合、通信遅延を回避するためにもCPU性能※2とメモリ容量の高いタイプがおすすめです。
また、2階建て以上の戸建てであれば、Wi-Fiが弱くなってしまう部屋にもスムーズに届くように、Wi-Fi中継器内蔵型の設置やメッシュWi-Fiが必要です。
そして、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐためのセキュリティ対策は、何よりも重要といえます。そのため、暗号技術のひとつである「WPA3」や、ソフトウェアを自動的に最新状態に保つ「自動ファームウェア更新機能」を搭載したタイプにすることで、リスクを軽減できます。
Wi-Fi選びのポイントのひとつは、次世代のMatterやThreadにも対応できるWi-Fi 6以降で、複数の通信方式に対応したルーターにすることです。すると、家電買い替えどきにも特別な設定なく移行がスムーズです。
※1 メッシュ(網目)のようにネットワークが繋がり、エリアをカバーする。
※2 CPUの性能は、パソコンの命令を処理するスピードと同時に処理可能な数で決まる。CPUは人間の頭脳や心臓に例えられることも多い。
住まいと生活スタイル別の最適なネットワーク
スマートホームのネットワークを選ぶときは、マンション・戸建てなど住まいの形や高齢者やペットと同居している場合など、生活スタイルの考慮もポイントです。そこで、住まいと生活スタイルの中で主なタイプ4つを例に解説します。
● マンション住まい(~50㎡)
間取りでいえば2LDKタイプが多い、50㎡の広さまでのマンションについては、Wi-Fi + Bluetooth の組み合わせが手軽で低コストのためおすすめです。50㎡までであれば、Wi-Fi の電波と Bluetooth の通信距離においての弱点カバーが可能です。さらに、同時使用で干渉するデメリット対策もしやすくなります。
コストも抑えやすく、スマートプラグとスマートスピーカーなら2万円以下で始められます。スマホで照明をON/OFFしたり「OK Google、明るくして!」と声での操作ができることで、消し忘れ防止と電気代節約に繋がります。
例:IKEAのスマート照明(Bluetooth)+Google Nest Mini(Wi-Fi)
● 戸建て(2階建て)
Zigbee + メッシュWi-Fi が鉄板です。中継機能で家中の信号をカバーできるため、浴室の湿度センサーから2階のエアコンまで連動するなど、階を超えた連動ができます。また、父のテレワークと母のスマート家電操作、子どものゲーム機を同時に使用しても安定します。
例:Aqaraハブ(Zigbee)+TP-Link Decoメッシュルーター
また、新しいスマート家電を購入した場合、電源を入れるだけで自動接続できるため、複雑で専門的な設定が必要ないのもおすすめポイントです。
● 高齢者との同居
Matter規格であれば異なるメーカーの家電を一つのアプリで一括管理できるため、複雑な設定がなく操作ミスも軽減できます。2024年以降、Matter対応機種が拡充していることから、家電を買い替えてもシステム全体の互換性を維持できるため、システム変更の必要がない点もおすすめです。
● ペット見守り重視
ペットの見守り重視であれば、有線LANカメラ + Wi-Fiセンサー のハイブリッドがおすすめです。24時間稼働の監視カメラは有線で電波干渉やバッテリー切れのない安定感を確保し、ペットの動線に置く人感センサーはWi-Fiで柔軟に配置できます。そのため、寝室やリビングなど各エリアの目的に合わせた通信方式にすることが可能です。
主なタイプ4つを例に解説しましたが、多数のスマート家電を同時に使用してもスムーズに動くこともネットワーク選びのポイントとなります。また、Wi-Fiは24時間接続するため、電気代の考慮も大切です。
スマートホームのネットワーク導入の基本ステップ3つ

スマートホームのネットワークの導入に必要な基本ステップは次の3つです。
- ネットワーク設計
- 中継機器の配置
- セキュリティ設定
それぞれのポイントについて解説します。
1. ネットワーク設計
通信方式の選択には部屋の広さも関係してきます。例えば、10畳(約16.5㎡)以下であれば、Bluetooth単体でも利用可能です。また、スマート電球など簡単な家電操作に最適です。ただし、電子レンジ使用時は接続が不安定になるため、家電は離して設置してくださいね。
また、20畳(約33㎡)以上の場合は、ZigbeeかメッシュWi-Fiが必須です。2階建てやLDKが分かれる場合、中継器を床から1.2m上の階段の壁に設置することで全てカバーできます。例えば、IKEAのスマート照明(Zigbee対応)は、リビングに1台ハブを設置することで家中の照明コントロールが可能です。
2. 中継機器の配置
中継機器を冷蔵庫の横に配置してしまうと、通信速度が最大80%低下することもあるため、冷蔵庫より上の棚に設置をおすすめします。また、電子レンジの近くもWi-Fiの電波とぶつかって通信が不安定になってしまいます。金属製品を含め、最低でも50cm以上離して設置するようにしましょう。
また、水回りの設置は電波を吸収したり湿気による故障の可能性があるためおすすめしません。ただし、設置せざるを得ない場合は防湿型ルーターを選び、床から30cm以上の位置に設置します。
3. セキュリティ設定
セキュリティ設定についてのポイントは、次の3つです。
- 初期パスワードは必ず変更
- 2.4GHz帯と5GHz帯を分離(家電は2.4GHz推奨)
- 定期的なファームウェア※更新
工事出荷時のパスワードは同じものが使用されていることも多いため、ぜひ変更してくださいね!また、Wi-Fiは2.4GHzと5GHzが一緒になっている場合も多くあります。そのため、Wi-Fiルーターで2.4GHzと5GHzを別々の名前(SSID)に設定することで、スムーズに接続できます。そして、定期的にファームウェア※更新によって不具合の調整やセキュリティの強化を行いましょう。
※ ファームウェアとは、ハードウェアを動かすためのソフトウェア(プログラム)。スマートプラグの頭脳にあたる。
スマートホームのネットワーク選びで快適さが変わる!
スマートホームに少しでも興味がわいた場合、まずは差すだけで使える「Wi-Fi対応のスマートプラグ」から手軽に試してみるのもおすすめです。
また、快適にスマート生活をおくるためにも、スマートホームのネットワーク選びは重要です。そのため、スマート家電を同時に使用してもスムーズに動く接続数や、24時間接続するWi-Fiの省エネはポイントとなります。
さらに、住まいの形や高齢者・ペットと同居など、生活スタイルに合わせたネットワークの選択によって、より快適な生活がおくれるでしょう。
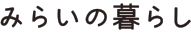

.jpg)